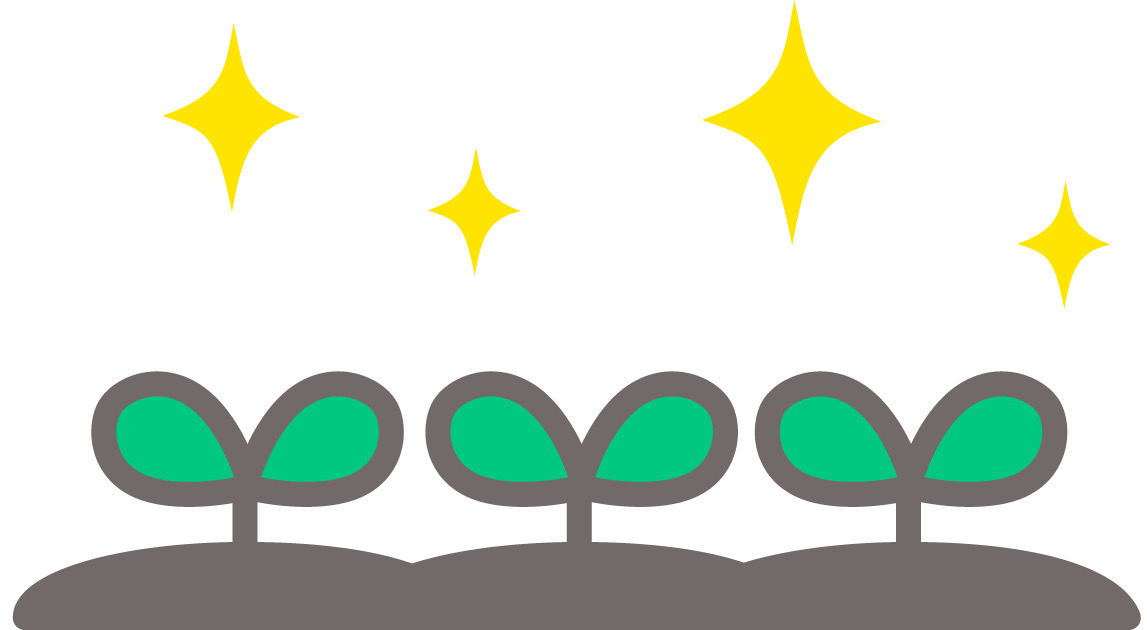にんにくは秋に植え付け、翌年の春に収穫しますが、冬の間と収穫直前には必ず、葉が枯れます。
これはにんにくの『生理的な現象』なので、収穫に影響ありません。
ですが『肥料不足や肥料焼け』と『病気や害虫』被害が原因で葉が枯れた場合は、収穫量が左右されるので注意が必要。
ここでは、『にんにく栽培で葉が枯れる』原因と対処法を詳しく解説します。
にんにく栽培で葉が枯れる3つの原因
にんにくは秋(9月中旬~10月中旬)に植え付け、春(5月下旬~6月中旬)に収穫しますが、栽培期間中に葉が枯れる原因はおもに3つあります。
①生理的現象:にんにくは2回、葉が黄色く枯れたようになる
まず1回目は12月~2月頃。(地域の温度差によってズレがあります)
にんにくは寒くなると成長がとまり、休眠状態になります。この頃出揃った葉は、寒さに当たって黄色くなることがあります。
次に葉が黄色くなるのは、役目を終えた5月頃。
にんにくの玉が熟成したことで、休眠に入り生育をやめ、下の葉から黄色くなり始めます。そして全体の2/3ほど枯れたら収穫のサインです。
②肥料不足とまく場所
にんにく栽培では、寒い冬を無事に越し収穫できるよう、肥沃な土を用意して種球を植えつけます。
成長を促すため、冬本番前の12月と、休眠から目覚める2月に追肥を施しますが、この2回の追肥を忘れると、肥料切れを起こしてがが枯れることがあります。
また追肥を施すとき、根元に近すぎたり量が多いと、根っこが害をきたし肥料焼けを起こして枯れてしまいます。
にんにくは種球の大きさに対し、意外と多くの肥料を必要としますが、タイミングとまく場所には注意が必要です。
光合成で作られる養分は冬の間、根と茎に蓄えられ、春になると収穫される実に蓄積されて大きくなります。
なので、寒くなって葉が枯れる前に、十分地上部分を成長させておく必要があるため、12月の追肥は重要な役割があります。
③害虫と病気
にんにくはコンパニオンプランツとして、他の植物の『虫よけ』に使われますが、にんにく自体にも害虫はつくものです。
なかでも厄介なのがアブラムシ。葉や茎に付いて、植物の汁を吸い成長を阻害し枯らせたり、ウイルス病・モザイク病などを媒介します。
風通しや水はけが悪いと害虫も繁殖しやすく、さらに病気にもなりやすくなります。
にんにくの葉を枯らさない対処法

にんにくが冬と収穫直前以外に、枯れてきたら要注意。時期や葉の症状を観察していきましょう。
肥料が原因の場合
にんにくは栽培期間中、2回の追肥を施します。
1回目は12月で、その後にんにくは休眠期に入るので、葉が枯れても肥料が原因ではありません。
気をつけたいのは2回目の追肥後です。
2月中旬、休眠から覚めた頃に2回目の追肥を施しますが、3月に入って葉が全体的に薄くなったら、肥料切れのサインです。この場合、速効性のある液体肥料を規定通りに薄めて与え、様子を見ましょう。
また、2回目の追肥直後や収穫には早い4月頃、葉色が悪くなったら肥料過多による『肥料焼け』の症状です。この場合、大量の水を与えて土の中から肥料を流し出すか、新しい土を足してなじませ様子を見ます。
害虫や病気が原因の場合
にんにくの臭いの元になるアリシンには、害虫を寄せ付けない効果があるといわれますが、必ずしも害虫被害を予防できるとは限りませんし、それが原因で病気になることもあります。
アブラムシや春腐病・葉枯病は、風通しや日当たりの悪い場所に発生しやすいため、にんにくを複数栽培するときは密植を避け、日当たりが良く、水はけの良い環境を整えましょう。
アブラムシ対策には
収穫直前の4月~6月、にんにくの葉にもアブラムシがつくことがあります。
アブラムシは繁殖力が強く、モザイク病など病気の原因ウイルスを媒介することもあるので、見つけたらすぐに駆除しましょう。専用の薬剤を使えば、駆除だけでなく予防することも可能です。
また、窒素が多い肥料を過剰に与えると、アブラムシがつきやすくなるので気を付けましょう。
にんにくの病気対策
【さび病】
カビの一種である菌に感染して起こる病気で、葉の表面に黒や褐色、白い斑点ができます。
初期段階なら、斑点のある葉を切り取って処分しますが、症状が全体的に進んでいると株ごと処分し、広がるのを抑えます。
【春腐病】
種球を植えつけ葉が2~3枚の頃から出始め、葉先が細くなります。症状が進行すると、葉の根元や種球まで腐らせ、広く感染する前に株ごと引き抜いて処分しましょう。
【葉枯病】
斑点や黄色みがかった細かい縦線が出たり、先端が枯れたようになります。早めに発見した時は、有効な殺菌剤を散布し、水はけを良くしてほどよく乾燥するよう心がけましょう。
活性剤のHB-101が病気と害虫に有効的
天然植物活性剤のHB-101は、植物自体の免疫力を活性化させることで病気に強くなります。さらに、成分に含まれる「フィトンチッド」という物質によって、外敵から植物を守る効果があります。
また、土壌に有効的な微生物の繁殖を助け、土の栄養バランスを保ち上質な土壌づくりにも役立つため、植物を根本から元気に育てる力があり、病気と害虫にも強いにんにく栽培に最適な活性剤です。
まとめ
にんにくは栽培期間中に2回、冬と収穫直前に生理的現象として葉が枯れます。他にも、肥料の過不足や病害虫の被害によって、葉や株が枯れることもあります。
ですが病気や害虫の場合、早めに発見して対処すれば感染を予防することも可能です。
にんにくは、野菜の中でも栽培期間が長いため、土中に根がしっかりと張らないと大きな球になりません。そのためには、肥沃でフカフカの土が必要で、良質な堆肥を多めに施し、20㎝以上深く耕して大きなにんにくの収穫を目指しましょう。